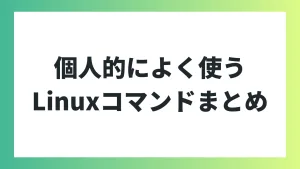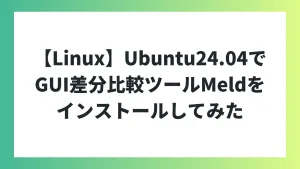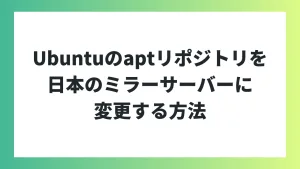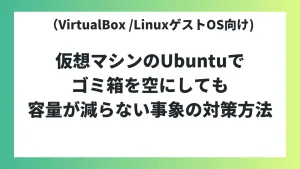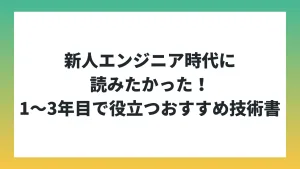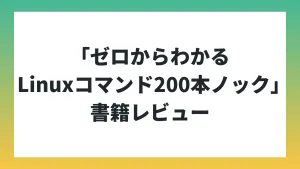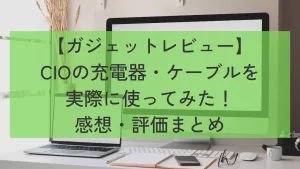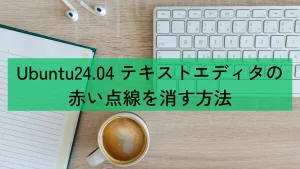はじめに
今回は「GNU Make 第3版」という書籍を購入し、その本を読んだ感想を書きたいと思います。

本書を購入した背景
実務でmakeを使用することになりました。
それまでプログラムのビルドはVisualStudioなどのIDEでビルドした経験が主だったため、makefileを使用したビルドは初めてでした。
完全に初心者だったので、本書で勉強しよう思ったのがきっかけです。
前回のマスタリングシェルスクリプトの紹介記事の時もそうでしたが、make関連の本も少なく、選択肢があまりないのがちょっと辛いですよね。
ネットで調べたりもしましたが、最近の記事のものも少ない印象です。
本書の感想
makeやmakefileを初心者が学びたいと思って最初に買う本ではなかった
最初読んでみて思った感想としては「自分のイメージしたものと違っていた」でした。
この本を購入する前、自分はmakefiteを書いた事ない状態でだったので、初心者の入門者のイメージで本書を購入しました。
しかし、この本は「makefileの基本的な書き方が一通りわかった人のステップアップの本」というイメージがしっくりくるような本でした。
makeのやり方やmakfileの作り方を一から解説を期待していた自分にとっては、基本的なお話がサラッとしていたので、これじゃなかったって感じました。
なので、私のようにmake,makefileについて初心者でmake,makefileの書き方を覚えたいなと思っている人にとって、この本を買う事はおすすめできないなと思います。
make,makefileの書き方について、ステップアップしたい人向けの本
ただ、本書を購入して「失敗したなー」と思ったわけではありません。
自分がmakefileの基本的な書き方を理解して、簡単なプログラムをmakeを使って実行できたタイミングで本書を読んだ時に「なるほど!」と思いました。
例えば、本書の第2章「ルール」の項目ではmakefileの細かいmakeのルールなどが解説されており、勉強になりました。
ネットでの情報のみじゃ理解できていなかった知識の補充ができました。
また、 makefileのincludeや組み込み関数、makefileで使用できる特殊な変数についてなど、幅広い内容が本書に書かれています。
ネットで調べてもすぐに見つかる内容ではないので、この一冊でいろいろなものがまとめられているのは良いなと思いました。
makefileの基本的な書き方しか知らない自分にとってステップアップできる内容でした。(と言っても後半の内容はそんなに理解できておらずまだまだ勉強中ですが。。。)
リファレンス的な扱いで要所要所で確認する使い方がオススメ
この本を読めばmake,makefileについての幅広い知識が身につくと思います。
それぐらい、濃い内容です。
ネットではここまで細かい内容は書かれていないので、困ったら本書を使う。というようなリファレンス的な扱いで本書で使用するのがいいなと思います。
オライリー系の書籍の内容は難しい(日本語的な意味で)
最後に、これはこの本にかぎった話ではないですが、英語を日本語に翻訳している以上、独特な日本語の表現になっていたり、説明が淡白になっていたり、逆に回りくどい表現になっています。
これはオライリー独特の表現だと思いますので、読む際には注意が必要です。
おわりに
最初の目的には合わなかったのですが、結果的には購入して正解でした。
make、makefileについてはネットでも情報が少ないと感じています。
ですので一冊に色々な項目がまとめられている本は貴重だなと思います。
気になった方はチェックしてみてください。