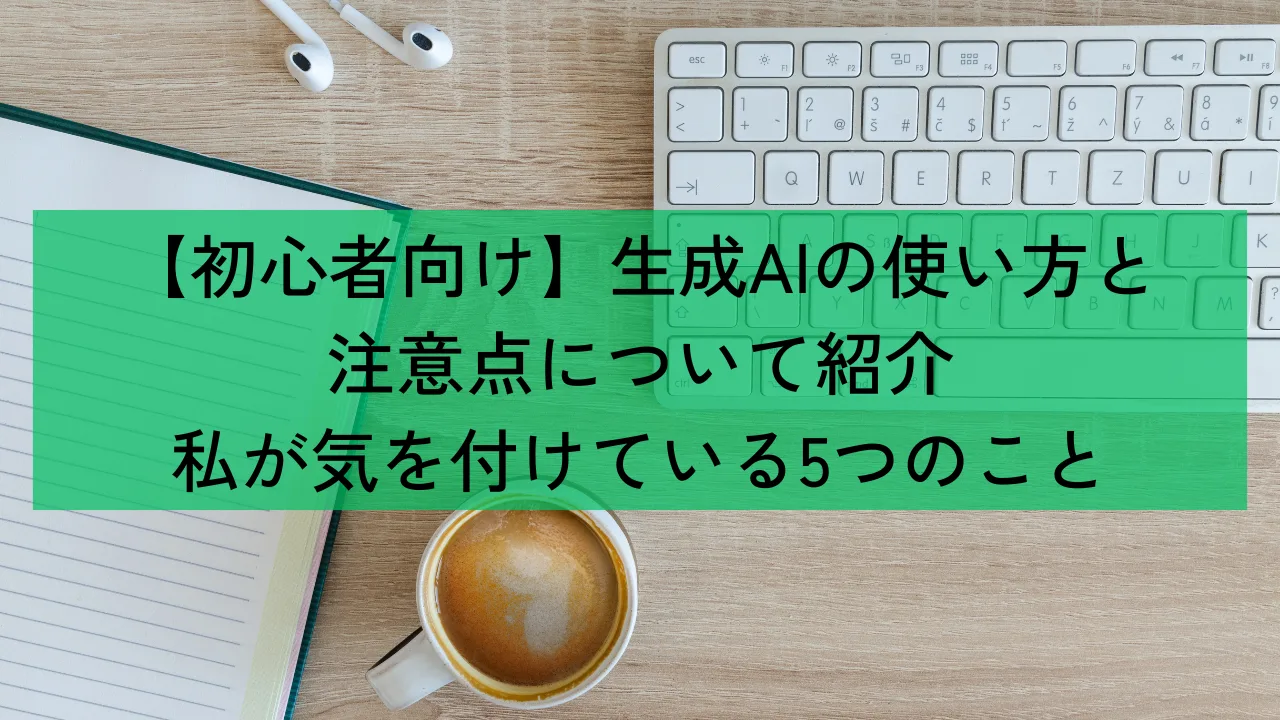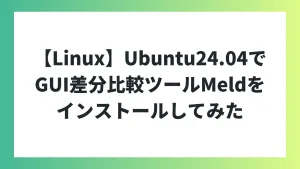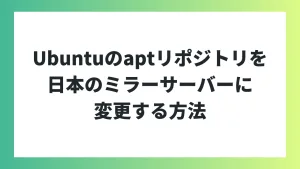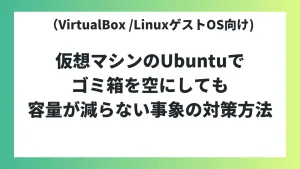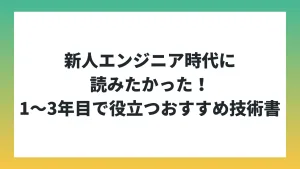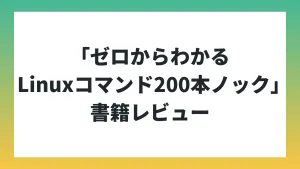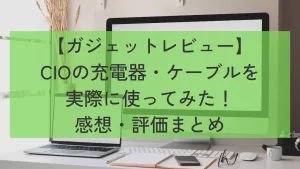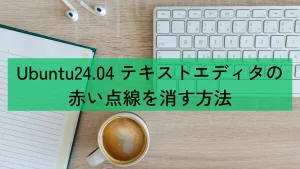はじめに
こんばんは。ちゃばです。
最近、ChatGPTやGitHub Copilotなどの生成AIがエンジニアの世界で急速に普及していますね。
私も乗り遅れないとAIについては勉強している最中です。
その中で今回は、私が生成AIを使うときに意識している5つのポイントをご紹介したいと思います。
生成AIについての書籍も読んでいます。読んだ書籍についてはレビューをしていますので、良かったらチェックしてみてください。
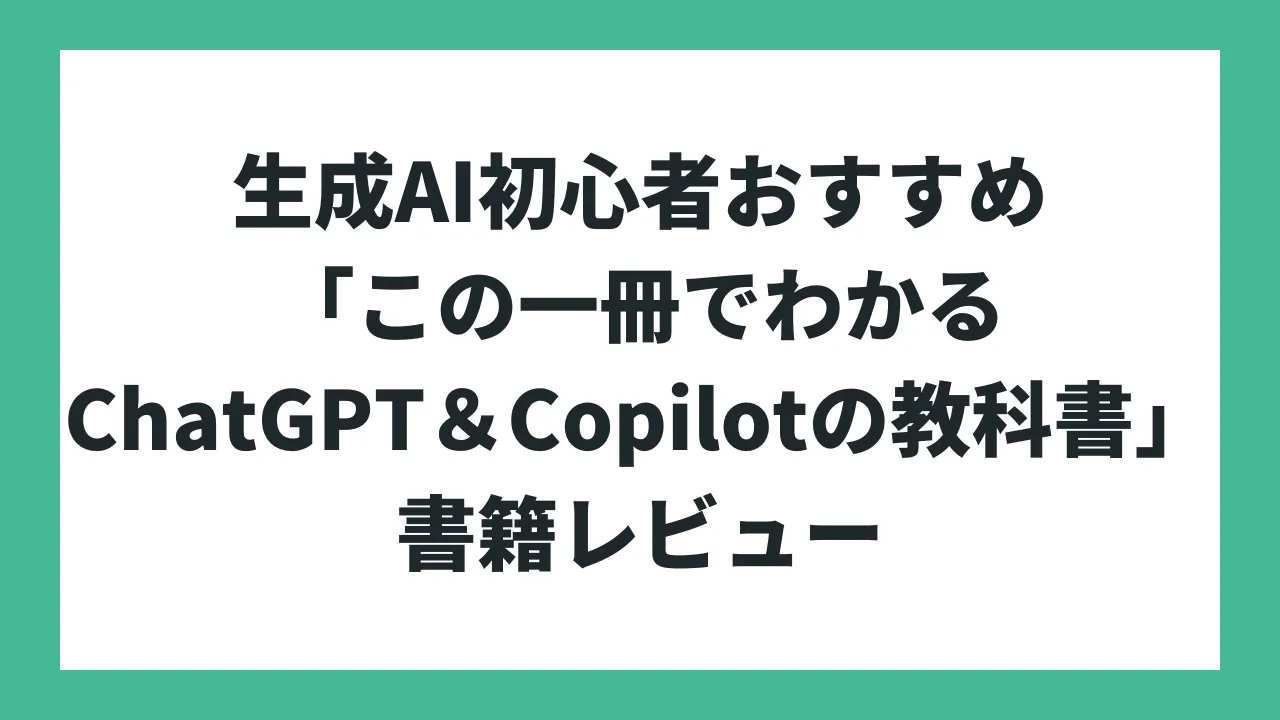
出力を鵜呑みにせず、必ず自分で確認する
生成AIの回答は優秀ですが、完璧ではありません。コードの提案も動かないことがあるし、文章の説明も誤りや誇張が混じっていることもあります。
ですので、しっかりと自分で確認することが大切です。
私が心掛けているのは、AIの出力を「ヒント」や「たたき台」として使い、最終的な判断や修正は自分ですること。「なぜこうなるのか」「本当に正しいのか」と出力に対して確認することが大切だと思っています。
良いプロンプトが良い結果を生む
これは私もまだ勉強中ですが、プロンプト(指示文)の仕方が重要だと考えています。
曖昧な質問では曖昧な答えしか返ってきません。私はなるべく具体的な状況や制約条件を必ず伝えるようにしています。たとえば「Python3で動く例をください」というようになるべく具体的な指示を行ったり、「初心者向けの簡単な説明をお願いします」といった補足の条件を付けたりといった工夫です。
それぐらいプロンプトは重要だと思っています。ただ、難しいのはまだどういったプロンプトが良いのか。という情報が少ないということなんですけどね。。。
セキュリティとプライバシーに常に注意する
生成AIに社内の機密情報や個人情報を入力してはいけません。多くのAIサービスでは、入力内容が学習データとして利用される可能性があります。ですのでセキュリティやプライバシーに関しては注意したいところですよね。
業務で使用する人も多いと思います。ビジネスプランだと学習されない生成AIサービスもありますが、自分が使っているサービスは学習されるのか、学習されないのかどうかを確認することが大切です。
依存しすぎず、自分の学習を優先する
生成AIは、わからないことをすぐに教えてくれる頼れる存在です。しかし、答えをそのまま使ってばかりでは自分の成長を妨げてしまう可能性があります。ですので、依存しすぎないことが大切です。適切な距離感というか。
文章作成なども便利だと思いますが、「自分でアウトプットする筋肉」が衰える可能性もあるのかなと考えています。
私は「まずは自分で考える」「AIの提案を自分なりに調べ直す」ということに気を付けて使用をしています。
AIはあくまで補助輪、自分の成長のためのパートナーと位置づけが個人的にはしっくりきています。
情報は常にアップデートすることを心掛ける
生成AIは進化が速く、昨日の情報が古くなることもしばしばです。
まだまだ成長していくと思いますので、常に最新の情報をキャッチアップしていくという姿勢が大切だと思っています。
参考
ChatGPT(2025/5/3 生成)
まとめ AIと共に成長する意識を持とう
いかかでしたでしょうか。
生成AIはまだまだ成長中の分野だと思います。ですので今後、気を付けることは変わってくるかもしれないですが、現時点で私が気を付けていることをまとめました。
私自身も今後も勉強していきたいと思います。